Vol.2 2005.7.8 - 2005.7.31
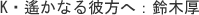
 自分が子供のころの父は、近所のこども達を集めて遠足に連れて行くような陽気なアンちゃんだった。今思えば、そのころの父はすで院展その他で一目置かれる才人ではあったようなのだが、芸大出の日本画家で張りつめたような顔で絵を描いている母の方がはるかに神秘的な人に思えた。自分が中学に上がるころ、1970年代始めに「顔を替える人」が出来た。 自分が子供のころの父は、近所のこども達を集めて遠足に連れて行くような陽気なアンちゃんだった。今思えば、そのころの父はすで院展その他で一目置かれる才人ではあったようなのだが、芸大出の日本画家で張りつめたような顔で絵を描いている母の方がはるかに神秘的な人に思えた。自分が中学に上がるころ、1970年代始めに「顔を替える人」が出来た。
この頃より彫刻の森美術館の企画展に呼ばれたりと急に有名になり多忙になった。父自身も「とうとう見つけた。死ぬまでこのスタイルで行く。」といったようなことを言っていた。続けて、「記念撮影」、「傍観者」といった傑作が続き、父は自信に溢れ、実に楽しそうに制作に打ち込むように見えた。父を尻に敷いていた感のあった母も「もう少しで、世界の名作になる」と太鼓判だった。今見ても、あの頃の数点は、それまでの彫刻とは全く違う70年代ならではの感覚がもられた、しかもすぐれた彫刻にしかない豊かで大らかな実りを感じさせる傑作だ。
山形の農家に生まれ旧制中学しか卒業しかしなかった若者が一流の芸術家として世に認められていくドラマのあった家庭は生活が年々豊かになっていく実感もあり、一人息子にとって誇らしく楽しいものであった。
しかしその後、ますます名声が上がるにつれて父が制作を楽しそうにやっているということがどんどんと減っていき、辛そうに仕事をするようになった。代表作といわれている「家族の肖像」もなんだか気に入らないようなことを言っていた覚えがある。
明るかった鈴木家は、名声の副産物である若い愛人の出現で陰りを帯び、母は鬱病になった。
再び、かつてのように楽しげに豊かな彫刻を苦もなく作り始めたように見えるのは、神経を延々と病み続けた母が1998年に死んで一人きりになった父が非業の死を迎えるまでの数年間だ。この展覧会に出品された「K・遙かなる彼方へ」はこの鈴木実最晩年の充実を代表する一点である。
≫ Back
|

