アートのある団地 - そうぞうする団地, アートのある団地, レポート
レポート:「いのだん、認知症でまちびらき」キックオフ講演会
終了しました 2025/11/06

暮らしながら、それぞれが”そうぞう”することを通じて、 少し先のまちを手づくりする。
取手井野団地ではじまっています。
井野団地や取手のまちで生活している方とともに、少し先のこの地域・この社会に必要な「仕組み」を実験し、団地を起点に将来の設計をつくっていくことを目指して活動している「そうぞうする団地」。
その中の活動のひとつ「いのだん、認知症でまちびらき」のキックオフとして、若年性認知症当事者の丹野智文さんを講師にお迎えし、講演会「認知症とともに楽しく生きる」を開催しました。
そうぞうする団地についてはこちらから
「いのだん、認知症でまちびらき」についてはこちらから
2025年8月24日(日)、猛暑のなか100名を超える方々が井野公民館へ足を運んでくださいました。やはりこの地域に暮らしているみなさんにとって関心のある話題なのだということを、講演会がはじまる前から感じます。
今回の講演会は、2部構成で行いました。第1部は、講師である丹野智文さんの講演、第2部は、地域のプレイヤーをパネリストとしてお迎えし、井野団地周辺地域での認知症に関する現状や取り組みなどについてのトークセッションです。

第1部
講師としてお迎えしたのは、若年性認知症当事者である丹野智文さんです。 丹野さんは、宮城県のネッツトヨタで働いていた2014年、39歳の頃に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。元々は営業のお仕事をされていて、診断を受けた後は社長と相談し、部署を異動して現在は事務のお仕事をされています。

診断と不安
営業の仕事をされていた当時、診断される5年前ほどから物覚えの悪さを感じていたといいます。その時は認知症だなんてつゆとも思わず、仕事をしっかりやりたいという思いから、ノートに仕事の内容を書くようにして対処していました。しかしながら、ノートを使い仕事をこなしていく中で、次第に細かい内容を書くことが増えていきます。部下にお客様が来たから行ってきなと言い送り出すと、しばらくしたらきょとんとした顔をして戻ってきて、丹野さんのお客様でしたよと言われたり、上司に怒られたりすることも増え、言い訳や嘘で誤魔化しながらなんとかこなしていたそうです。
そんなある日、それまで一緒に働いていたスタッフの名前が出てこなくなりました。これはさすがにおかしいと思った丹野さんは、病院へ行くことを決めます。
初めは脳神経外科へ行き、検査をしました。その結果、大きな病院で検査を受けることを勧められ、物忘れ外来へ。その時には、病院へ行くために仕事を抜ける必要があったので、職場にも初めて事情を話します。
そして、入院して検査を受けました。お医者さんから告げられたのは、アルツハイマーの疑いがあるが、この若さでは診断したことがないという言葉。大学病院でもう一度検査を受けることになります。
大学病院への検査入院までの間は仕事へ戻り、同僚や上司に相談をしました。その人たちからは、「俺も同じようなことがあるよ。ストレスじゃないの?」「アルツハイマーだったら大変なことだぞ」と言われ、丹野さんはその時、「アルツハイマー=終わり」だと感じたといいます。これからどうなってしまうのか、不安でいっぱいな一方で、自分は元気だし何か他の軽い病気なのではないかと思う気持ちもあったそうです。
そして迎えた大学病院での検査入院。1から検査をやり直そうと言われ、少しほっとします。しかし、脳裏にはいつも「アルツハイマー=終わり」という言葉が消えませんでした。
検査を終え奥さんとともに結果を聞くと、お医者さんからは「アルツハイマーで間違いありません」と言われました。丹野さんはこの時、ああ、みんなと同じ物忘れじゃなかったんだと思ったそうです。奥さんには心配をかけたくないと思い平然と話を聞きました。そんな中ふと隣を見ると、涙を流す奥さんの姿が。その姿を見て再び「アルツハイマー=終わり」という言葉を思い出しました。奥さんが帰り1人になった時、丹野さんの目からも涙が溢れてきました。
「認知症=終わり」なのか?
診断を受けた翌日から、薬の服用が始まりました。担当の先生が毎日病室に来てくれたので、「寝たきりになってしまうのか」「会社にはどう話せばいいか」など気になったことは全て質問しました。先生はしっかり話を聞いてくれたので心は落ち着きましたが、夜になるとやはり不安で眠れなかったそうです。インターネットで認知症について調べてみると、若年性認知症は進行が早く、何もわからなくなり、寝たきりになると書いてありました。よくない情報ばかりが目につき、退院後どうしたらいいのか、会社をクビにならないか不安になる日々が続きました。
退院後、そういった不安なことを聞くために、区役所へ向かいました。しかし、窓口で言われたのは40歳未満では介護保険が使えないということ。欲しかった情報をもらうことはできなかったといいます。
丹野さんは子どもたちのためにも会社を辞めるという選択肢はなかったといいます。そんな中社長に相談をすると、体が動くならなんでも仕事はあるから戻ってきなさいと言われ、総務人事グループへと異動することになりました。
とはいえ、認知症になった自分が新しい仕事をできるようになるのかは不安だったそうです。認知症だからと情けをかけられるのは嫌で、みんなに認めてもらえるようにと仕事をしました。記憶が悪いだけなので、丹野さんはやはり全てをノートに書きながら仕事をしたそうです。2冊のノートを使い、1冊には仕事の段取りを全て書き、もう1冊には今日やること、やったこと、聞いたことを全て書いていました。今では同僚がノートを貸してというくらい、マニュアルのようなものになっているといいます。
工夫しながら働いていた丹野さんでしたが、1年ほどは新しい部署に馴染めませんでした。しかし、ある日同僚に、丹野さんは何に困っているの?と聞かれたので、正直に困っていることを話したところ、周りの対応が変わり仕事がしやすくなったそうです。
また、とある夏の日に丹野さんが「暑いよね〜ビールでも飲みたいよね」と言うと、「丹野さん病気でしょ?お酒とか飲んじゃいけないのでは?」と聞かれたといいます。お医者さんからはダメとは言われていないことを話すと、じゃあ飲みに行こう!と誘ってくれるようになったそうです。
このような経験から、周りの人たちは、丹野さんが何ができないのか、誘っても良いのかわからないから戸惑っているのかと気づき、自分ができること、できないこと、やりたいことを周りにきちんと伝えるようにしました。今では遊びに行こうとみんなが誘ってくれるといいます。仕事も、通勤の電車を間違えて遅刻してしまうことや、デスクの位置、上司のかたの顔がわからなくなることもありますが、みんなに聞きながら仕事をしているそうです。
そのように毎日働いていると、ある日社長に呼び出されました。怒られるのかとドキドキしながら社長の元へ向かうと、
「丹野くん、毎日笑顔で来てくれてありがとう。君が笑顔で仕事を続けてくれることが、他の社員にとっても、もし自分が病気になった時も仕事を続けられるという安心に繋がっているから、会社としても個人としても、君のことを応援しているよ」
という言葉をもらったそうです。その言葉がとても嬉しく、おかげで今でも働き続けられているといいます。

認知症とともに生きる
丹野さんは、認知症になってから多くの人との出会いがあったといいます。その中でも、笑顔で元気な認知症当事者との出会いは大きく、この人のように生きてみたいと思ったことが、前向きに生きるきっかけになったそうです。認知症になったことを悔やむのではなく、認知症とともに生きるという道を歩むことにしました。認知症になったからといって悪いことばかりではなく、家族と過ごす時間が増えたり、多くの人の優しさに触れたりすることもできました。そんな経験を経て、「認知症=終わり」ではないのだと思うようになったといいます。
病気になって一番辛いことは、家族に心配をかけていることだそうです。また、生活の中では、丹野さんが認知症の当事者だと誰も気づかないことが辛かったといいます。初期の認知症の人は、見た目ではわからないため、普通に話しかけられるし、頼まれごともします。しかしながら、やろうとしてもできないこともあります。その結果、全てが嫌になってしまったりもするそうです。
そこで、丹野さんは病気をオープンにすることにしました。最初は、アルツハイマーに偏見を持っている人が多いと思っていたため葛藤していたといいます。オープンにすることで家族に迷惑がかからないか、娘たちがいじめられないか、不安でした。
そこで、両親に相談してみると、「悪いことはしていないのだから、私たちのことは気にせずオープンにしなさい」と言ってもらえ、娘たちに「友だちにも知られてしまうかもしれないよ」と言うと、「パパは良いことをしているのだからいいんじゃない?」と言ってくれたそうです。オープンにすることで、サポートや支援を受けることができました。
しかしながら、偏見があるからとオープンにできない人がいるのも事実です。そうした偏見は、まずは自分の心の中にあります。周りから何も言われたことがなくても、何と言われるのかを気にしてしまうのです。丹野さんの場合は、助けてくれる人の方が多かったから、どんどんオープンにできたといいます。
学生時代の部活動の仲間と会う機会があった際に、丹野さんは、昔のことを忘れていないかな、みんなのこと覚えているかなと不安を抱えながら会場まで向かいました。ご飯を食べながら病気のことを打ち明け、「次に会う時、忘れていたらごめんね」と笑いながら言うと、「大丈夫、俺たちが覚えているから」と言ってくれたそうです。忘れないように定期的に会おうとも言ってくれました。 その言葉で、心配が全て吹き飛んだといいます。私が忘れてもみんなが覚えていてくれる、それでいいじゃないかと思ったそうです。
認知症になっても、周りの環境さえ良ければ笑顔で楽しく暮らせるのです。丹野さんは、環境が一番大切だと感じているといいます。年代は関係なく、人と人とのつながりが笑顔にしてくれたと話してくださいました。
する・されるの関係ではないパートナー
周りにいる人たちは、介護者ではなくパートナーだと丹野さんは言います。できないことをサポートしてもらいながら、できることを一緒にするーーそんな関係性だそうです。今までは、認知症になると何もできなくなるからやってあげなければと思う人が多かったのではないでしょうか。しかしながら、介護が必要なのは本当に重度になってからです。認知症と診断されると、まず介護保険の話をされてしまうから、すぐに介護が必要になると連想されて決めつけられていたのではないかと、丹野さんは考えているそうです。
丹野さんは、認知症本人への寄り添い方について、会場にこう伝えました。
「できることを奪わないでください。時間はかかるかもしれませんが、待ってあげてください。一回できなくても、次はできるかもと信じてあげてください。」
認知症当事者の方も、できた時は自信を持てます。自信を持って行動することは大切で、良かれと思い全てをやってあげると、本人はむしろ自信を失い、本当に全てができなくなってしまうのです。失敗をしながらでも、自信を持って行動すること。周りは失敗しても怒らず、行動を奪わないこと。そうすることで気持ちが安定し、進行を遅らせるのではないかと丹野さんは言います。
本当に危険なことについては注意が必要ですが、その注意も話し方や言い方で本人の感じ方は変わります。本人も失敗したことはわかっているのです。ただ、なぜ失敗しているかがわからないだけなのです。
当事者の方が、失敗ばかりするので迷惑をかけたくないと思い、自分でやることを諦めてしまうと、何もしたくなくなり鬱になってしまいます。そのため、失敗を恐れずに自立する気持ちを強く持つことが大切です。
そして当事者がその気持ちを持つためには、周りが自立を奪わないことが重要になります。自立とは、サポートしてもらいながらもできることは自分でやること、自分の意見をはっきり言って自分で決めること、できないことはできないと周りにサポートを求めることです。守られるのではなく、目的達成のために力を借りて課題を乗り越えていくことが、自立につながります。
守るという行為は、周りの人たちの心配と優しさからくるものだと思います。しかし、それが結果的に機能の低下を招いてしまうのです。
認知症だと診断されたら、ひとりで出歩くのを禁止されたり、財布を取り上げられたりしてしまうこともしばしば。管理と監視の対象になってしまうことが不安につながり、出かけなくなってしまいます。もし外ではぐれた時、財布や携帯を使い続けていないと、何も手段を考えられなくなってしまいます。奪われない環境が、命を守ることにつながります。
認知症といっても、様々なタイプがあり、段階があり、人によって環境も違います。しかしながら、ひとまとめにされているところがあるのが現状です。目が悪い人が自分に合わない度数の眼鏡をかけたとしたら、見えなくなるし症状も進んでしまうのと同じように、認知症も人それぞれ必要なサポートは違います。
「認知症という病気ではなく、目の前の人をきちんと見てください。介護が必要な人には、適切な介護や介護支援が必要です。しかし、そのような重度の認知症になるまでの過程は誰にでもあります。」
丹野さん自身も、当事者やその家族と関わる中で、家族が当事者の代わりに話してしまったり、本人の隣でこの人は何もできなくなったという話をしてしまったりする人を見てきたといいます。そういった態度を取られては、当事者もイライラするし落ち込むに決まっています。認知症になると怒るようになると言われますが、周りにいる皆さんが怒らせてしまっていることをわかってほしいと丹野さんはいいます。
そして支援者は、当事者の暮らしをより良くすることに注力してほしいということも語られました。支援者が家族の困りごとを中心に話を進めてしまうことは多々あり、その解決のために当事者は施設や精神病院へ入れられてしまうこともあるそうです。挨拶も家族へする、名刺も家族にだけ渡す、当事者との方とは、何を困ってますか、など尋問のような会話しかしない。そのような対応で果たして支援をできているのでしょうか。介護保険を使うのは家族ではなく当事者なのです。
多くの人は、ご本人が認知症になる前の姿を追い求めてしまいます。そのため、診断されることを恐れて病院に行きたがらない人もいます。しかし、認知症になったとしても、早期診断、支援、社会参加から、楽しい人生を再構築することはできます。丹野さんは、認知症になって車の運転こそ諦めてしまいましたが、講演活動などで人生が大きく変わりました。認知症になっても新しく道は作ることができるのです。認知症になったとき、病院で薬を渡すだけではなく、本人や家族が安心して暮らせるように、当事者の話をきちんと聞いて、色々と教えてあげてほしいと丹野さんはいいます。どこに何を聞いたらいいかが分からない状態で不安が増すことで、うつなどの他の病気になってしまうこともあります。
認知症は恥ずかしい病気ではありません。誰でもなり得るただの病気です。できなくなることもありますが、できることもあります。今は認知症ではない人でも、いつなるかわからないのです。
丹野さんは参加者の皆さんへ、人ごとではなく自分ごととして持ちかえってほしいと話しました。現在は認知症の仲間を支えていきたいという思いを持って、啓発活動や講演活動をしていらっしゃいます。以前は自分の仕事をしながらやっていたそうですが、社長と話し合いをし、今では認知症にかかわる活動が仕事になっています。丹野さんはこれまでずっと”笑顔で過ごす”といってきましたが、顔面麻痺で笑顔が作れなくなったことをきっかけに、いまは認知症とともに”楽しく生きる”といっているそうです。しかし、心の中はいつでも笑顔でいたいといいます。安心して認知症になれる世界を一緒につくっていきましょう、という言葉で、丹野さんの講演は幕を閉じました。
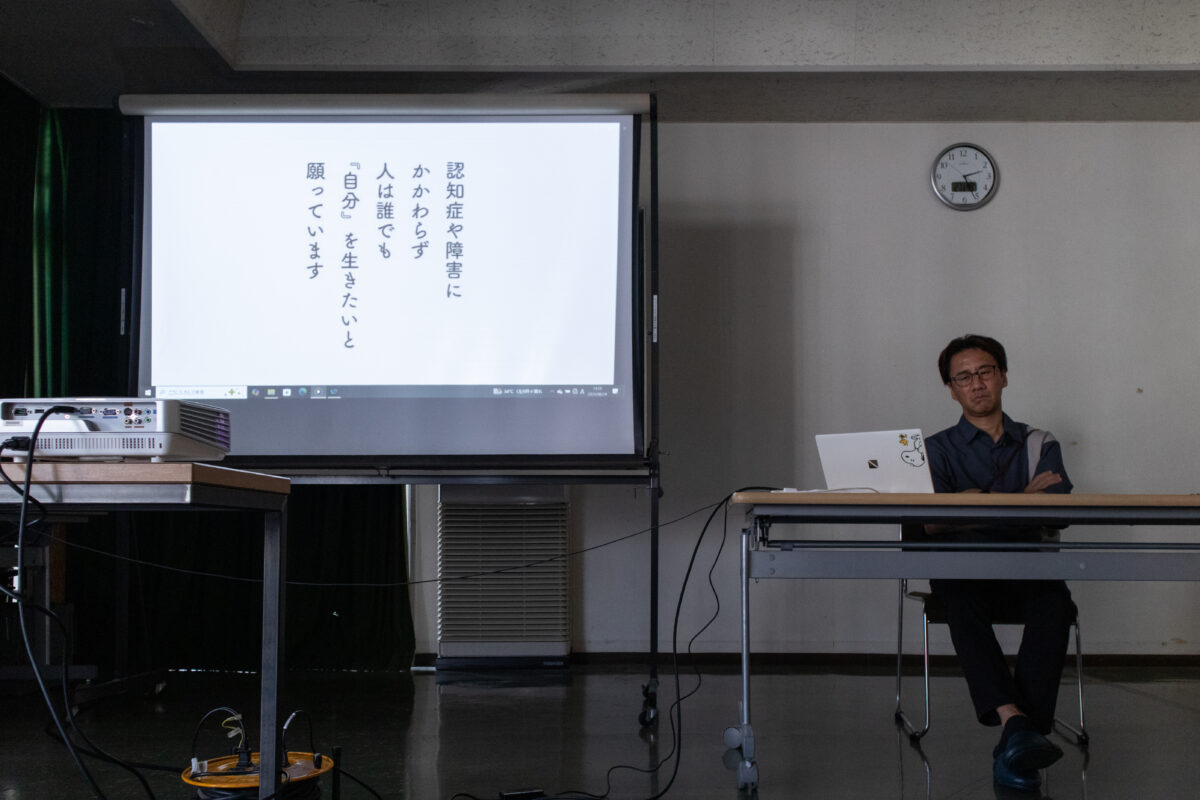
本人ミーティング
丹野さんは若いから喋れるんでしょと言われることがあるそうです。しかし、そんなことはありません。丹野さんの主催する本人ミーティングの様子をおさめた映像を見せていただきました。
青空の下、丹野さんがひとりの男性とおしゃべりをしながら歩いています。ここまでは歩きとバスで来て、帰りは歩いて帰るという男性。あっちこっち通るのが楽しくて、3時間くらいかけて歩くそうです。とっても健康的ですね。遠いけれど、それがひとつの楽しみになっていると、マスク越しですが笑顔で話しているのが伝わりました。
会場へ、続々と参加者が集まってきます。参加者は皆、認知症の当事者です。
そして、本人ミーティングが始まり、それぞれの抱える思いを話していきます。
みなさん穏やかに、笑顔で話していて、集まった仲間たちと話すのが楽しい、救われるという声が多くありました。
みなさん過去には認知症という言葉への抵抗感や、偏見に対しての不安などを抱えていたそうですが、本人ミーティングを通して仲間と出会い、認知症であることは気にせずに、やりたいことをしながら生きていらっしゃるのだというお話をたくさん聞くことができました。
動画はこちらからご覧いただけます。ぜひ、当事者の生の声を聞いてみてください。
(出典:一般社団法人認知症当事者ネットワークみやぎ)
第2部
第2部は、認知症の方やそのご家族と関わる現場を持っていらっしゃる6名の方に登壇いただいてのトークセッションです。現場で感じる課題、またそれを乗り越えるためのアイデアなどを、各々の経験や丹野さんの講演をもとにお話いただきました。そんなトークセッションの様子をお届けします。
登壇者
- 丹野 智文さん
- 添田 博之さん(若年性認知症ご本人・取手市在住)
- 田中 寿さん(取手井野団地自治会長)
- 伊藤 由紀さん(居宅介護支援事業所 水彩館 水彩館 管理者/主任介護支援専門員)
- 野口 俊信さん(地域包括支援センターはあとぴあ センター長)
- 藤井 康彦さん(「オンライン・オレンジカフェいこい」代表/そうぞうする団地実験パートナー)
モデレーター
- 羽原康恵(取手アートプロジェクト 包括ディレクター)

羽原
第1部の講演での丹野さんのお話から、認知症の当事者の方だけでなく、周りの環境やつながりをどう作っていくかを考えさせられました。
では、この取手で、井野団地で、認知症になってもならなくても、診断された後も、その方が自分らしく生きていける環境はどうしたら作っていけるのだろうかということを、それぞれの現場を持ってらっしゃる皆さんとお話ししていきたいと思います。
まずは、第1部の丹野さんの講演を受けて、どのようなことを感じたかというところと、自己紹介として普段やっていらっしゃることをお伺いできればと思います。
伊藤
小文間にある水彩館という福祉法人にて、お家で暮らす方のケアマネジャーをしています、伊藤と申します。私たちは普段、介護認定をお持ちの方の対応をするのがほとんどになっていますが、丹野さんの講演を聞いて、目の前の人を見るというところが、初心に帰るとそうだよねと感じました。
私たちはどうしても、できないこと、お困りのことを中心に見て、どういうサービスにつなげるかに注目してしまいがちなのですが、ご本人を見るということと、本当の事実というところをとても考えさせられました。
今日のトークセッションを通じて、今どういうことができるかというところを一緒に考えていけたらなと思います。
野口
地域包括支援センターはあとぴあでセンター長をしています、野口と申します。
はあとぴあは、井野団地の担当をさせていただいている地域包括支援センターです。丹野さんのことは以前から存じていましたが、今日直接丹野さんのお話を聞けて、改めて伝わってくるものがたくさんありました。
私たちも普段仕事として認知症の方の支援に携わっている中で、一番難しいなと感じるのは、支援者であったり、そのご家族であったり、周囲の方の認知症に対する意識を変えること、そしてご本人への意識は変えないことです。
認知症と診断をされたことで、いろんなことを奪われていく場面をたくさん見ています。そうじゃないだろうということを、様々な場面でお伝えしても、変わらないことがあります。できることを奪わないであげてほしいということを伝える難しさを、丹野さんのお話を聞いて改めて実感しております。
今日会場を見渡して、いわゆる支援者側の人間があまりいないなということの寂しさを感じております。本日のトークセッションは、いろいろな問題提起をさせていただく機会にもなるかなと思ったのですが、登壇者の方々とのお話も通じて、これからどういう形で井野団地や井野地区の支援の形を作っていけるか、みなさんと一緒に考えていけたらと思っております。
添田
認知症当事者の添田と申します。私は、昨年の 8月に認知症と診断を受け、そこから治療を開始しました。
認知症になって最初に思ったのが、診断して認知症だよと言われたときに、認知症っていう言葉を知らなかったので、まずそれが衝撃でした。会社の同僚や社長から、仕事でミスが多くなったと言われたことがありまして、大学病院で認知症の診断を受けました。その結果、認知症ということで結果が出ました。8月が仕事の契約の更新日だったのですが、そのまま退職という形で現在に至るというところです。
その後に、本人ミーティングというのを妻が取手の市報で見つけまして、どういうものかわからないけれども、まあ何もやらないのもなということで、まず問い合わせをしました。そこで、藤井さんから今度こういう会があるからおいでよと誘われて、行ってみました。
行ってみたところ、わりと和気あいあいとした形でお話をされているというのがすごく印象的でした。そういう様子を見ると、気持ちは救われました。それまでは誰にどういうことを聞けばいいの?と手探りの状態でしたので、一筋の光が差したような感覚でした。それ以降は月1回、本人ミーティングに参加しています。
藤井
オンライン・オレンジカフェいこいの代表で、添田さんも参加いただいている本人ミーティングを市役所さんと一緒にウェルネスプラザでやっています、藤井と申します。
丹野さんのお話の中にもあったのですが、本人ミーティングでは、必ず認知症のご本人に向けてお話をするというところは意識的にやっています。というのも、実は丹野さんのオレンジドアを勉強しに仙台まで行かせてもらい、丹野さんのお話やなされていることを勉強させてもらいまして、そこで学んだことを活かしているというところです。
講演では、認知症になったら何もできなくなるというような偏見が自分自身にもあるというのが印象的でした。私自身も含めて、そうじゃないという意識があっても、どうしても偏見が認められないみたいなところもあると思うのです。それはしょうがないけれど、(偏見が)あるということを自覚していることが大事なのかなというふうにも思っています。井野団地での活動の中では、皆さんとそのあたりも共有しながら進めさせていただければなと思っています。
田中
井野団地自治会の田中です。井野団地はですね、取手市の中でも高齢化率が1、2番を争っているところなんですね。75歳以上の方が33%ぐらい、65歳以上、いわゆる高齢者の方が52%という状況にあります。その状況を踏まえて、今日のお話の中で感じたことは2つありました。
1つ、認知症は防げないということですね。これは防災の観点と同じだなと思いまして、最後に丹野さんが言われたように、友達づきあいが大事だなということと、連絡網をどうするかということを考えておかなければと感じました。
2つ目としては、昔はがんにかかるとみんな隠していましたよね。ところが今、がんになってもみんなオープンじゃないですか。認知症も昔のがんと同じように、人に言いにくい環境にあるのだけれども、丹野さんの自ら名乗って友達と連絡を取っているというお話を聞くと、やっぱりこれからは認知症もオープンにするのは良いと思います。がんの場合ステージの1から5まであるように、認知症も程度は上から下まであると考えていくと、これから私たちも高齢者が増える中で、避けて通れない問題だと思って付き合っていきたいと思います。
団地でも高齢者のためのいろいろな施策をやってはいるのですが、課題もまだまだ感じます。井野団地はURの賃貸住宅です。したがって、居住者の出入りがあるということが1つ。また、個人情報保護法というのが2003年にできまして、2005年以降、入ってくる人の名前をURさんも公表できないのです。2005年より前までは居住者の名簿があったのですが、現在は名簿が全然できていない。隣に誰が住んでいるのかもわからない。そういう状況の中では、防災もできないということです。
皆さんとの今日のお話を通じて、こういった課題について知識を広めながら取り組んでいきたいと思います。

羽原
井野団地の現状について、自治会長の田中さんからご紹介がありました。自治会さんから見るとやはり情報がなく、つながりがなく、防災の面でも難しさを感じている状況だということですね。
現在サービスやサポートの部分で関わられている地域包括さんと水彩館さんとしては、そういった井野団地の現状をどう捉えていらっしゃるか、お聞きしてもよろしいですか?
野口
田中会長からお話がありましたように、井野団地は私たちが担当している地域の中で高齢化率が1番の地域になります。約2,500名の高齢者の方がいらっしゃる中で、一ヵ月あたりの平均の相談件数が260件程度になっています。そのうち訪問が約60件、地域包括支援センターから出向いて相談対応を行っています。
その中で、一人暮らしの方や高齢者だけの世帯の方が非常に多いなというのは日々実感しております。そして、名簿がないという話がありましたが、地域包括支援センターでは、行政の住民基本台帳ネットワークシステムなどである程度調べて、ここにこういう方がいらっしゃるんだなという情報の把握はできるのですが、やはり何かがなければなかなかお伺いする機会もありません。URさんの方から、この一週間新聞がすごくたまっている、異臭がする、もしかしたら、というような情報を頂いて、時には同行させていただくこともあるというような現状で、本当に高齢者の方が多いエリアだなと感じております。
井野団地に認知症という診断を受けた方がどのぐらいいらっしゃるのかというデータはとっておりません。ただ、関わる方で、おそらくこの方は検査を受けたら認知症という診断を受けるだろうな、という方はたくさん知っています。
丹野さんのお話の中でもありましたが、やはりどうしても65歳以上の方であれば、すぐ介護保険認定の申請ということをお伝えしがちではあります。ですが、私たちも関わる中で、この地域にもう40年以上お住まいになっていて、地域の風景とか雰囲気とか、ご近所の方の関係とか、いろいろな要素があり、ちょっと心配もあるけれど、全然まだできていることもあるもんね、ということで見守っている方もたくさんいます。
そういった中で、いろいろな課題を感じることもありますが、今日をきっかけに地域のみなさんの意識も少し変わっていったとして、じゃあ私たちはどういう形で関わりとして入っていけるかというところも考えたいですね。
現状としては、潜在的な認知症の予備軍の方であったり、もしかしたらという方は非常に多いということを感じております。
伊藤
私たちは介護認定をお持ちの方の対応をすることが主となっています。その中でケアマネージャーとして感じることとしては、野口さんのお話や会長のお話にもあったように、やはり80代、90代のお一人暮らしの方、あとは高齢世帯の方がとても多いなという印象です。そして、認知症のことで言いますと、かなり症状が進行して周りの人から見ても心配な状況、または一人でお出かけされて戻れなくなって、警察から保護されてというような案件でつながることが多くなっている気がします。
先ほども新聞の話がありましたけれど、外から見て、例えば同じ洗濯物がずっと干しっぱなしであるとか、新聞がすごくたまってしまっているとかいうことが、戸建てのお宅よりも、団地や集合住宅の方が周りから分かりづらいというところも、傾向としてあるのかなと思います。
また、利用者のお客様やご家族の方からは、以前は付き合いがあったけれども、だんだん同世代の方がいなくなってしまったとか、話すきっかけがなくなって、周りに話せるような人がなかなかいないというようなお話を伺います。なので、私たちがお宅に伺って、介護保険のことやその他市のサービスなどの説明を差し上げた時に、そういうものがあるんだ、知らなかったという方が多いです。介護保険は払っているけれど、どういうシステムなのか、どんなことがあるのか、誰に相談したらいいのかっていうのが全然わからないんですね。
また、自分が介護状態になるまでは他人事で考えたことがなかったけれど、実際になる前からこういうのがあるということが分かっていたら、もうちょっと早く相談できるところがあったんじゃないか、というようなお話を伺うことが多いなというイメージです。
例えば、ゴミ出しでいつも会う方が、前は身なりとかをきちんとおしゃれをしていたのに、ちょっと気にならない感じになってきたなとか、燃えるゴミの日なのにどうも缶を持ってくるとか、ちょっとおや? と思う変化というのが、周りの方は普段の状況をご存じでないとなかなか気づきづらいので、普段からのそういう顔の見える関係だとか、孤立しないようにというところは大切だと感じます。
私たちも、包括支援センターというところがあるんですよ、よかったら連絡してみてくださいと言いますけれど、やはり知らないところなので、そこまではいいですと尻込みされるような方が結構いらっしゃいます。なので、私がお客様のお宅にお邪魔した際に、近所に心配な人がいるので一緒に連れてきても良いか?というようにつなげていただき、地域の相談窓口というところで包括さんにつなげたり、市役所の方と連携をしたりというところもあります。私のお客様で、例えばゴミ捨ての時に今日燃えるゴミだけどなんかない?とご近所の方が声をかけてくださって、ゴミ出しができている方などもいらっしゃいます。
みんな足が弱くなったりしていくのと同じように、認知症というのは誰もがなり得るものなので、他人事じゃなく自分事として考えられていたらいいのかなと思っています。

羽原
現状の共有をありがとうございます。
仲良くしていた友達が認知症かもしれないとなったら、心配が先に立ち、どこかへつなげられるといいなと考える心の動きが生まれるとは思うんですけれども、例えばあまり関係が深くない近所の人に対しては「認知症だ、認知症かもしれない」と言ってしまうことへの恐怖感のようなものが多分あって。でもそれは、認知症になっても断絶してしまうわけではなく、ちゃんとその場でずっと生活ができるように仕組みがあるのだということを伝えられる思考回路があるかどうかのような気がします。
これからは5人に 1人が認知症ということで、私も皆さんもいつその状況に直面するかわからない中で、認知症の診断を受けた初期の方がいらした時に、どういう場があるとつながりを自ら絶たないだろうかとか、家族が孤立しないかとか、どういうふうにつながりを求めていくといいかという部分を丹野さんと添田さんにお聞きしたいです。
丹野
まず自分が認知症になった時に、人に認知症って病名だけ伝えると、人は離れます。これはなぜかというと、何ができて何ができないかわからないんですよ。だから、みんな優しさでそっとしておこうと思って離れちゃうんですよね。
私もね、さっき講演でも言ったように、お酒を飲みたいのに、認知症だからお酒は飲んじゃダメなんじゃないかって周りが思っていたんですよね。なので、できることと、苦手なことと、やりたいこと、この3つをちゃんと伝えない限り、人は離れるってことに気づいたんです。
仮に時間の感覚がわからなくなったら、ちゃんと伝えておけば、前日や当日に、明日集まりあるよとか、今日集まりあるよって連絡をもらえるようになるんですよね。私の場合は人の顔がわからなくなるので、次会う時忘れるねって言っておくと、忘れてもこわくないんですよ。認知症の人は、自分の症状はちゃんとみんな知ってますから。物忘れがあるとか、人の顔がわからないとか、わかってます。
ただ認知症かどうかじゃなくて、自分にできること、できないこと、自分がやりたいことを伝えるべきだし、周りの人たちは見方を変えてほしいんです。“認知症の丹野智文くん”と見るか、“丹野智文君に物忘れがあるよね/道に迷うよね/人の顔わからないよね”と見るかで全然変わりますよね。
みんな“認知症の〇〇さん”って見ちゃうとおかしなことになるんですよ。そうじゃなくて、目の前のおばあちゃんが物忘れがあるよね。じゃあ、そこを支えようって思えば、病名は関係ないんですよね。そういうふうに私は思っています。
羽原
先ほど、会場からのコメントシートで、認知症という言葉が先に立ってしまうけれど、自分自身をみてもらうためには、認知症当事者はどういうことに留意するのでしょうかというご質問が来ていて、まさに今お話しいただいたことだと感じました。
丹野
できることと、できないことと、やりたいことをきちっと伝える。
羽原
それは丹野さんはご自分で整理されたんですか?
丹野
そうですね。最初の1年半、誰も何にも誘ってくれなかったんですよね。お酒も誘ってくれないし。
今はね、全然飲みますよ。先生からは飲み過ぎは注意ねと言われているけれど、どのくらいが飲みすぎかわからないから、いつも飲みすぎるんだけどね。お酒飲んで認知症が進行するんだったら、もう進行してますよ。でもこうやってお酒も飲んで楽しくしてるから、むしろ進行が遅いんじゃないかなと思って。
だから、これがいいとかこれが悪いとかじゃなくて、ちゃんと自分のやりたいことをやるってことが大切かなと思ってます。
羽原
好きなこと、やりたいことが何かをしっかり考えて、周りにどんどん言うといいってことですね。
丹野
そうですね。できる、できないは別にしても、言っておくと、「あ、じゃあこの時誘ってあげようかな」って思ってもらえます。
仮にテニスをしようとなった時に、「認知症の人って体を動かせるのかな?テニスってきついのに…」と思われるかもしれません。でも「テニスがしたい」と言っておけば、機会があったら誘おうかなってなるんですよね。
だから自分のやりたいことは常に言い続けないと周りの人たちはやっぱり気づかないんですよね。それが大切だと思います。
羽原
確かに、認知症の方へどう声をかけたらいいのだろうと思った時に、何がやりたいか、今後何をしたいかという声のかけ方をひとつ学んだなというふうに思います。
丹野
そして1つだけ。「何やりたい?」と聞いて「何でもいい」と答える当事者はいっぱいいます。この人たちは、ほとんどが財布を持ってない人です。本当にそう思いました。
財布を取り上げられたら、何をやりたいとか何を食べたいとか、自分でも気づかなくなります。そのくらい、財布って大きいんですよね。だから、財布を取り上げないということがまず大切です。そのうえで、何がやりたいか、何が食べたいかと聞くことが必要です。

羽原
なるほど。もう今日ここにいるみなさんは絶対取り上げない。いいですか、みなさん。財布は取り上げない。
では続いて添田さんにお伺いしたいと思います。認知症当事者ということを、この場でもお伝えいただいていますし、周りの方にも伝えてらっしゃるというのはお聞きしてるのですが、ご自身がリラックスしているなとか、周りときちんとつながれているなという居場所はありますか?
添田
そうですね。リラックスできる場所というのが、家庭もそうですし、何でも話せる仲間というか、友達というか、そういう人たちがいればいいかなと思います。
あとは、あまり認知症だ認知症だって言わないでほしい。日曜日、運動教室に行ってるんですけど、結構ご高齢の方がいらしてるんですね。僕は僕であまり気にせず、「実は認知症なんだよね」なんて軽く言っているんですけど、「ああそうなの?大変だね」ってたった一言で終わっちゃうんです。そういう環境っていうのかな。あまりこう、しつこくなくあっさりっていうのもいいのかなという感じがしました。

羽原
今すでに反省をしました。添田さんと丹野さんと呼ばせていただくことにします。
リラックスできる、個人のやりたいことを好きなこと、やってみたいことを聞ける関係性というのは、すぐにはなれないと思うので、普段から近しく、その人が何が好きで、どうしたら心地よくいられるのかというようなことを共有できる場が必要だなと思います。
そういう場を作っていくというのが今回のプロジェクトの趣旨でもあるんですけれども、野口さん、地域包括支援センターとしてやってみたいなとか、これから手掛けてみたいなと思っていることはありますか?
野口
地域包括支援センターでは、認知症サポーターの養成講座や、認知症のことをお話ししてほしいということで、講座の依頼を受けます。
そこでよく、今まさに話題に出た、もし自分が診断を受けた時に、どういったことを諦めたくないか、どういったことをこれからもやりたいか、ということを聞いたりしています。その中で、嵐のコンサートにはずっと行きたいとか、これからも娘と旅行に行きたいとか書かれていたり、私はサッカーを見るのが好きなので、誰か試合に連れて行ってくれないかなと書いたりするんですけど。そういった講座や研修などの、少し堅苦しい場に出てきてくださる方って、まだ意識が高い方なんですよね。
もちろんそういうところでのこういったやりとりも大切かとは思いますが、団地の中の今は空いてしまっている店舗をどう活用しようか、というお話が出ていることを羽原さんから伺いまして。地域包括支援センターって、いろんなところで宣伝をして頑張ってやっているつもりなんですけど、まだまだ届いてないなというところもあるので、URさんの空き店舗に出張する形で出向かせていただければ、地域みなさんとの距離が近くなるのかなと思っています。
地域包括支援センターには、保健師であったり看護師であったり、私のようなケアマネージャーであったり、社会福祉士といったいろんな職種が所属してますので、高齢の方だけじゃなくて、若い方でも病気のことで受診に行くべきかどうか悩んでいる方もいらっしゃるだろうし、子育てで悩んでいるお母さん、お父さんや、不登校でお家に引きこもっているお子さんなど、幅広く受け入れられるような、保健室のような機能を団地の中に作れたら面白いかもしれないですね。
今回の「いのだん、認知症でまちびらき」と少しリンクするのですが、地域包括支援センターとしても、団地の皆さんやURさん、取手アートプロジェクトさんなどとと力を合わせて、地域の方が安心していろんなことを相談できる場が作れないかなと思っているところです。

羽原
ありがとうございます。お次は田中会長、団地に新しい繋がりを作るというところ、いかがでしょうか。
田中
今まで私ども高齢者の中で、顔の見える場所ということで、ふれあい居酒屋や健康麻雀などもやってきてるわけですね。残念ながらふれあい居酒屋はコロナで中断して、復活できてないんですけども。やはりお年寄りが集まる場所は必要なんですよね。
そのために、ぜひ私も動きたいと思ってますから、健康相談室のようなことを団地の中でやりたいという提案があれば、自治会としても一定の条件を満たせば集会所が無料で借りることもできますので、是非お願いしたいと思います。
羽原
ありがとうございます。「そうぞうする団地」の活動で、団地で誰かに何かを届けたいという提案の中に夜のバーをやりたいという方がいらっしゃいました。ふれあい居酒屋のような場も、一緒に運営しながら、コロナ以降の再開という形にもつなげていけるかなというふうに思いました。
では、藤井さん、今回実験パートナーになっていただいているのですが、今後どういった場を団地に作りたいかというところを、ドリーム含めて、お聞きできますでしょうか。
藤井
その前にですね、私が本人ミーティングをやっている中でお聞きしたエピソードをご紹介をさせていただければと思います。井野団地周辺にも、いろんなサロンとかサークルとか、ご高齢の方が楽しめる、交流できる場が結構あると思うのですが、とある方が、ご主人が認知症になられた時に、そのご主人はサークルで吹き矢を楽しまれていたようなんです。
ところが、認知症になって、吹き矢をする時にやや時間がかかってしまったりして、奥様が「あなたもうみんなに迷惑だからやめなさい」ということで、やめさせてしまったらしいんですね。その後ご主人は、せっかくの楽しみがなくなってしまったので、元気がなくなってしまい、今奥様はそのことをすごく後悔しているとおっしゃっていました。
そのお話がすごく印象に残ってまして、今すでにあるサークルであるとか、ふれあいサロンとかで、今まで来た人が認知症になられたのかなみたいなこともあったとしても、変わりなく接してまた来てもらえるようにしていただくといいのかなというふうに思いました。
そして、これからやりたいことについて。1つは、本人ミーティングです。今はやれる人とやっておりますけれども、足が不便でなかなか来れませんというような方もいらっしゃるので、この井野団地の中でも本人ミーティングという集いの場を作っていきたいなと思っております。
それからもう1つ、こういうものは、やるから来てくださいよと何度も言ったところでなかなか来れないというのは共通認識だと思います。その中で、認知症の方でも、高齢の方でも、ご自分の得意なこととか、まだまだやりたいこととか、好きなことっていうのがあると思うんですね。そういう方に、「来てください」ではなくて、「あなたのやりたいこと、好きなことを教えてください」「あなたと一緒にやりたいです」「あるいはあなたに学びたいです」というような形で、支援するのではなくて、認知症の方や高齢の方に教えてもらうような、まだ仮称ですが「いのだんオレンジ塾」という塾のようなものをやりたいです。そうすれば新たな人の繋がりや交流が生まれるのかなと思ってます。
そして最後に、今私たちは実験パートナーということで手を取らせていただいて、「そうぞうする団地」で活動させてもらっていますが、私たち以外にもいろんな実験パートナーの方がいらっしゃるんです。みなさんとても素晴らしい企画をいろいろとやられてますので、単発ではなくつながるような形で、一緒にできることがあればやりたいですね。また、はあとぴあさんなども専門家なので、いろいろ教えていただきながら一緒に進められるかなというふうに思っております。
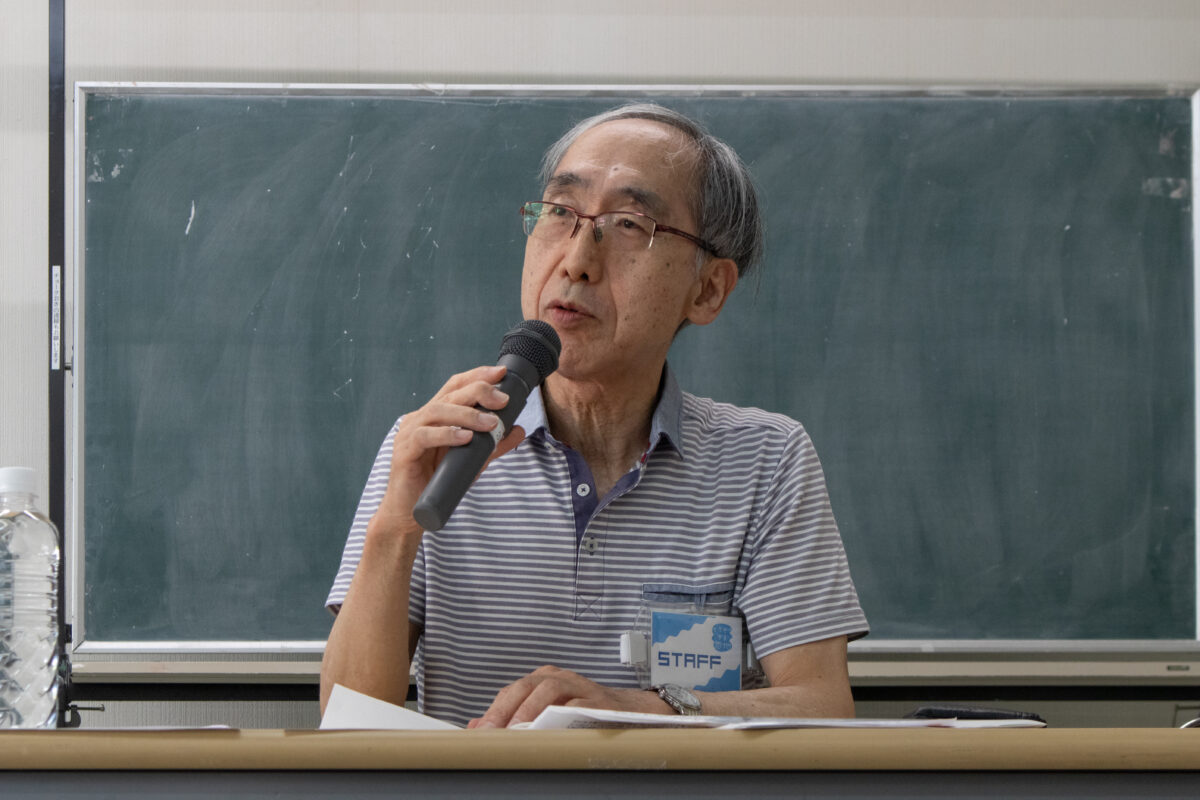
羽原
藤井さんの「いのだんオレンジ塾」というアイデアに深く共感をしたところがありました。さっき丹野さんが見せてくださった映像の中にも、ケアされる側、支援する側、というふうに立場を固めてしまわないっていうワードがあったと思うのですが、それをひっくり返すような試みだと。認知症の当事者でも、そうでなくても、誰もが提供する側になるし、学びをシェアできる側になるというところにすごく共感しています。私たちも、地域の中で生きていくときに、役割が固まってしまわない状況を作ることができるといいなというふうに思っています。
ここからお一人ずつコメントをいただく形で、最後は届いている質問カードへのフィードバックに進めてまいりたいと思います。では、まず伊藤さんから、当事者の方が周りが気付く状況になってからではないと支援につながらない現状があるとおっしゃっていた中で、その前の段階にどういった仕組みがあるといいなというふうに思っていらっしゃいますか?
伊藤
そうですね。先ほどもお伝えしましたが、私たち介護支援事業所のケアマネジャーというのは、介護認定をお持ちで、さらに介護のサービスを何か使いたいと思っている方がつながることが多いんですけれども、その中でお話をしていくときに、“介護される”のではなくて、もっとやりたいことがあるのに、なかなかそれとマッチするサービスがないということが課題になることがとても多くあります。
例えば、私のお客様でも、62歳の男性の方がいらっしゃるんですけれども、ご家族としては、家の中にずっといて、足が弱くて心配なのでデイサービスへ行ってほしいということで、ご本人は嫌だとおっしゃっていたのですが、体を動かしませんかというところで行ったんです。しかし、その内容が「こんな幼稚園みたいなことやってられるか!」というような内容で、ご本人はとてもご立腹。もう絶対こんなところには行かないと、逆に殻を閉ざしてしまいました。じゃあどんなことをしたいのかと私が聞きましたら、その方は犬の散歩をしたいっておっしゃったんです。ただ、ご家族は「もうお父さん危ないからやめて、前に家がわからなくなってわんこだけ帰ってきたことあるでしょ」と言っていたんです。
丹野さんのお話でもありましたが、心配なことに関しては、「やらないでください。私たちがやりますから、いいですよ。」というのが本当のその人の自立なのかというところで、反省点だと思います。そして望ましくない対応をしてしまうということに対して、ちゃんとしたことを知らない状態だと、私たちは知らないからわからない、怖い、ちょっと自分とは違うというふうに思ってしまいがちなんですが、情報を知って、正しく理解するということと、その方の声をきちんと聞くということが大切になると思います。
私の祖母もですね、85歳で母のところに来たんですけど、環境が変わったことで、夕方買い物に行ったり、散歩しに行ったりすると帰って来られないことがよくありました。もう施設に入るしかないという話になり、当時私は認知症グループホームの管理者をしていたので、私のところの施設に入れてという話になったんですけど、うちの祖母はそういうのは絶対嫌だってなりまして。裁縫をしていた人だったので、うちの施設にボランティアで来て、裁縫教室をしてもらうことにしたんです。
施設では、私が入る前は針は危ないからやっちゃだめだとなっていたんですが、きちんと管理をすれば、皆さん好きなことは続けられると気づきました。みなさんすごく集中していて、認知症が進行して会話も難しい方が、とても上手に雑巾のなみ縫いをされていて、それをご家族に見せたらすごく喜ばれて、ご本人も褒められたことに対して喜んでいました。他にもお孫さんの入学のバッグにお名前を刺繍していた方もいました。
できることってたくさんあると思うんですよね。そういうところに着目できるかというのも、周りの者としては大事かなと思うので、一人でも多くの方に自分ごととして捉えていただき、正しい理解を伝えていただけると、暮らしやすいまちになるのかなと思っています。
羽原
今のお話で、先ほどの丹野さんの“守るが奪うことにならないか”という言葉がすごい頭に浮かんだのですけれど、コメントをいただいてもいいでしょうか。
丹野
実は仙台ではね、認知症の人の女子会を作ってるんですよ。なんで作ったかっていうと、男性介護者の悩みで一番多かったのが奥様の下着を買うのが大変ということ。でもね、本人に聞いたら誰一人買ってきてほしいと言わないんですよ。どうですか?みんな、お父さんが自分の下着買ってきたら。嫌でしょ?(頷く会場内の女性たち)
ね、嫌だよね。全然マッチングしてないんですよ。男性介護者は買いに来る。本人は買ってきてほしくない。これを役所に持っていくと、今度はね、男性介護者がどう買いやすくするかって考えるんですよ。違うんですよ。本人が買いに行かないといけない。ということで、女子会を作りました。
同行者が1人と、当事者 5、6人で下着や服を買いに行く。その後美味しい紅茶やケーキを食べる。参加者の中に、デイサービスでお風呂に入りたくないっておばあちゃんがいたんですよ。その理由は、ただ単に旦那が買ってきた下着がダサすぎてやめて欲しかっただけで、自分で下着を買うようになったら入るようになったんですよね。これはどういうことかというと、高齢になろうが認知症になろうが、恥ずかしいっていう思いがちゃんとあるってことなんですよね。
別にこれ、支援じゃないんです。1人の同行者はあえて若い人にしてもらったんですよ。なぜかというと、お年寄りに合わせる必要はなくて、若い子が食べたいケーキ屋さんとかに行くと、おばあちゃんたち食べたことないから、すごくキラキラするんですよ。この間何食べて来た?って聞いたら、パンケーキだって。いいよね。だからもう私たちは、国の支援とか関係なしに、本人たちとやりたいことを普通に地域でやれるようにしてるんですよ。支援ってなると、何かあったら誰が責任取るの?とかって言うけど、友達と遊びに行く時は保険かけないもんね。皆そうでしょ。でもなぜか、認知症になると保険をかけましょうみたいなこと言うんですよね。
山登りがしたいという時に、包括の人に言うと、包括の人が登れる山を考えちゃうんですよ。富士山とか登れないよ、普通の人は。だから、私たちは本人がどこを目指してるかっていうのをちゃんと聞くんですよ。それで、富士山だったら富士山を登れるプロの人に任せちゃうんですよ。そうすると、プロの人が認知症のことを学ぶんですよ。勝手にサポーター養成講座になるんだよね。こういうのを地域でやってます。
だからあんまりね、深く考えない方がいいですよ。若い子と一緒に買い物行ったりするのもいいし、山登りがしたいって言うんだったら、地域の山登りやってる人につなげるのがいいし、歌を歌いたいって言ったら、カラオケ教室につなげればいいし。あんまり支援、支援じゃなくて、地域にあるコミュニティとどうつなげるかが大切なような気がします。
羽原
ありがとうございます。皆さんうなずいてらっしゃいますね。支援っていうワードをNGワードにするといいのかもって思ったりもいたしました。
では、最後に添田さん。昨年の夏から診断されて1年で、こうやって外に出てきてくださっていることに、私自身も添田さんからすごく勇気を感じると思っているんですけれど、まだ外に出てこられていない方にどんな場があったらいいと思いますか。
添田
そういうことはあまり考えたことがないんですが、1つ、担当の先生から運動しなさいって言われていることがヒントですかね。もともと運動自体は嫌いではなかったので、渡り船みたいなところはありました。それが発展して、大体朝1時間ちょっとは必ず歩いてます。自分ができることで楽しそうなことをやるみたいな感じですね。苦手なものはちょっと引いちゃいますけど。あとは、家の中に猫がいるので、それとじゃれてるみたいな。それも一つ気分転換にはなります。
最初、認知症と言われた時にもかなりへこみましたので、「なんで俺が」というのは感じましたけど、今はそういうことはあまり気にせずに、なるようになるかなみたいな感じですかね。
羽原
ありがとうございます。いくつか会場からコメントを頂いているんですけれども、皆さんの参考になるだろうなと思うものをひとつ紹介させていただきます。特に丹野さんへの質問ですが、「丹野さんが明るく前向きに生活されていることに心強さを感じます。支えとなっているのは何ですか?」というシンプルなご質問です。
丹野
支えとなっているのは家族ですね。
私が診断された時は39歳。子どもは小学校5年生と中学校1年生でした。この子たちをどう育てたらいいかということで本当に悩みました。毎晩毎晩泣いてばかりいました。でも、この子たちがいたから働き続けたんですよ。今も働いてるんです。うちの子はもう25歳と23歳になったので働いてますけど、まだ住宅ローンが残ってるんですよ。だから、もう少し頑張らなきゃいけないんですよね。
家族がいなかったら、私は会社を辞めて家に引きこもっていたかもしれない。子どもがある程度卒業していたら、もしかしたら働かなかったかもしれない。でも子どもが小さかったからこそ、どんなことをしてでも働こうと思いました。やっぱり働くって簡単ではないんですよ。ものすごく大変なんですよ。それはプライドとかがもうズタズタになるぐらいなんですよね。周りがやっている仕事がかっこよく見えて、自分がやっている仕事がどんどんどんどん情けなくなってくる。でもそこにプライドは持たない。働き続けるってことにプライドを持ってやっているのでね。私、50代ですから体は動くんですよ。女性が重い荷物を持っていたら、走ってでも持ってあげる。そうするとちゃんと理解されるようになってきて、認められるようになるんですよね。だからさっき添田さんが言ったように、自分ができることを頑張ることで、周りが認めてくれるようになるんですよね。
で、質問なんでしたっけ? 今喋りながら忘れちゃった。
羽原
支えは何ですか?という質問なので、ズバッと答えていただきました。
丹野
家族です。はい。
それと、最後に1つ。よくこういうところに来ると、“認知症になっても安心な取手市にしましょう”とかって書いてあるんですよね。認知症になってもではないですよ。ここにいる皆さん1人1人、自分自身が安心して認知症になれる取手市にしなきゃいけないんです。
自分自身が安心して認知症になれるまちをぜひ一緒に作っていきましょう。ありがとうございました。

羽原
本当に皆さんありがとうございました。今日はものすごく色々なキーワードを共有できて、会場の皆さんと目がすごく合うのがすごい嬉しいと思っています。
認知症に安心してなれるまちを作る。それをまずは井野団地で作ってみようというのがこれから始まっていきます。まずは情報をみんなで知っていくということが、すごく大事だなと思っています。なので、情報を受け取りたい方、参加したいな、面白そうと思った方は、どんどん踏み込んでいただければと思います。
「いのだん、認知症でまちびらき」の情報をお届け!
活動についての情報をメールでお届けいたします。こちらのフォームよりご登録ください。
認知症の方もそうでない方も暮らしやすい、認知症に安心してなれるまちを一緒につくりましょう!
レポート:田中天眞音
撮影:山下紗弥
