レポート, 半農半芸, 半農半芸 - 藝大食堂, TAPの現在地, TAPの現在地 - 定点観測 事務局長エッセイ
定点観測 #3 ショーケースの展示から:生きづらさを投げ出す優しさについて
終了しました 2022/01/19
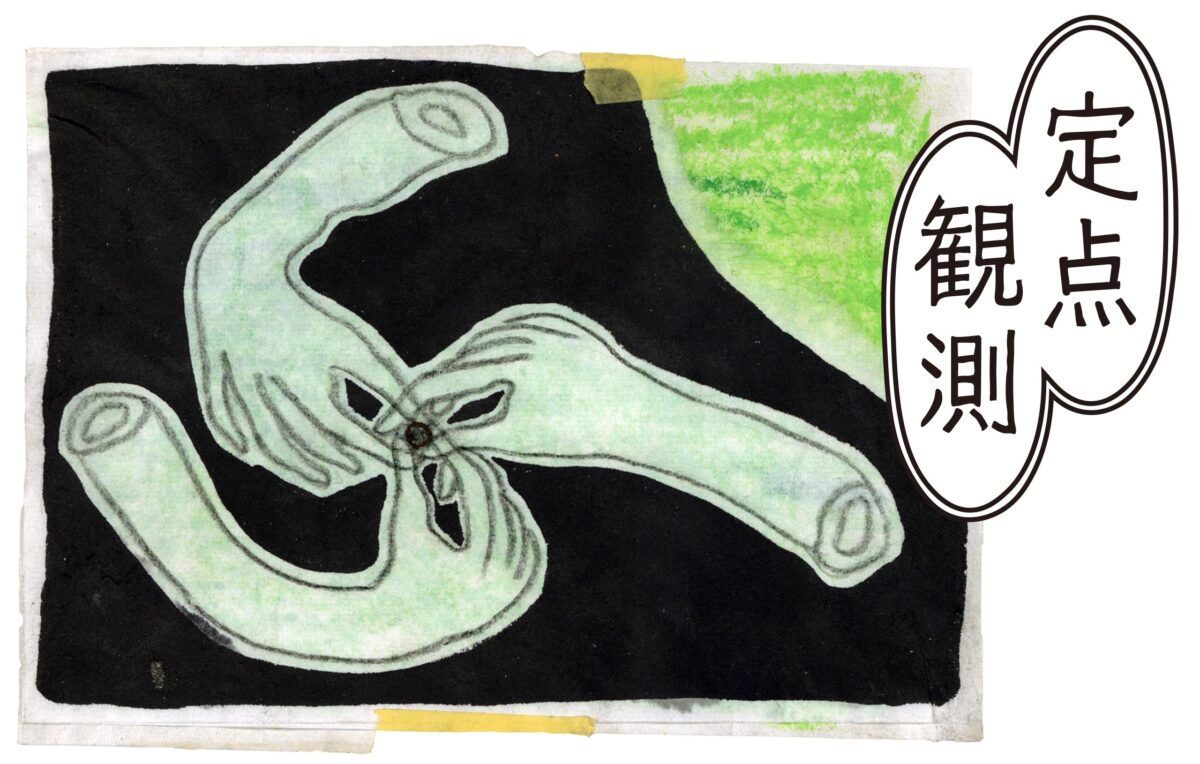
TAP事務局長(兼藝大食堂で時々番頭、兼ヤギの目メンバー)の不定期エッセイ第3回です。
定点観測 2022.1
個人が持つ「生きづらさ」を他人の目の前に投げ出す、その優しさについて
12月初旬まで藝大食堂で開催されていたショーケース&ショーケースインザスクリーン。ここで紹介した2作品が、そこに生身の人そのものが投げ出されているように感じる展示だったことについて書き留めておきたいと思う。
藝大食堂発足当初から続くショーケースは、食堂の運営がTAPに切り替わり使われなくなった元食品サンプルケースを舞台に始まった。このサンプルケースでの展示(ショーケース)を小沢剛さん、モニターでの映像上映(ショーケースインザスクリーン・2019年〜)をその時々のパートナーが、それぞれ出展者をセレクトし展示をおこなっている(2021年度は先端芸術表現科の新明就太さんとグローバルアートプラクティス専攻の石川洋樹さんのコンビネーション)。若い芸術家の表現活動を紹介する場として、今年度は11組の作家が作品を発表した。
11月末から12月にかけての会期は、神谷絢栄さん、寺田健人さんによる作品展示だった。異なる表現手法をとりながら、この2作品とも、性に紐づいてその人個人が経験してきたことを見る側に共有するものだった。そのためこの約1ヶ月は、作品を通じて露わになる、入口は個人的な、しかし社会の中で隠されてきた性のことについて、日々意識を向けられる時間でもあった。

ショーケースインザスクリーン#12. 寺田健人 Terada Kento《想像上の妻と娘にケーキを買って帰る》2021年
LGBTQ+のことについて、実は以前、TAPの事務所で古参のスタッフーー戦後すぐの生まれの方、と強い言い合いになったことがある。彼らの存在を、どうしても生理的に受け付けられないといったその大先輩に対して、生きる時代が違うことで、受けてきた教育も得られた情報も異なることはすっ飛ばして、自分が強い非難を口にしたことを覚えている。性的指向は個人の意思ではなくてナチュラルなものなんだ、と。ナチュラルなものを勝手に受け付けないと存在を否定する権利なんてない。
けれどそう叱責した自分の言葉には、実体験でないハッタリや身勝手さが混ざっていることも知っていた。理解しているふりではないか、結局自分にもバイアスがあるはずだ。当事者のつらさや経験については、知らないことが多すぎるし、想像しきれることはないだろう。
私自身も幼少から小中学校までの頃、ジェンダーは明確なものだと疑わなかった。どのクラスでも、どの会社でもどの組織でも、1/10の誰かは生きづらさとともに笑っていたし、今も笑っているんだろうと思う。%で語るものではないが、日本ではAB型の人口と同じくらいの割合で悩む人がいても、その悩みが露出してこないのは、その友人たち、見知らぬ誰かがつらさを抱え込んできたからだ。
またLGBTQ+のことだけだけでなく、「性」のことで受ける生きづらさは、あくまで個人の抱えることとして、社会では見えなくされてきた。当事者にならない限り、知ろうとしない限り、どんなにその当事者の人たちがしんどくてつらくても、見えてこない。
誤解を恐れずにいえば、今回の展示は、「性」に由来して自身が経験してきたリアルな生きづらさを穏やかに非当事者に分けてくれる2作品だったと思う。それを優しさと感じるのは私の勝手だろうとも前置きした上で、これらのつらさをシェアしてくれる行為は、やはり優しさだと思えた。
寺田さんの作品では、写真や動画の中で典型的な父親像を作家自身が演じ、独りで被写体として映り込む。見る人が感じる違和感は、自分も他人も、社会の中での性に基づいて演じているのでは?というささやかな問いのはじまりになる。周りの人々の性が実はとても不確かであることに気付かされる。
一方神谷さんは、自身が大学入学前に受けた性暴力被害に由来するPTSDに向き合う中で、言葉にできない自らの体験をどう他の人と分けうるのかを考えるための一つの実験の再構成を展示していた。
 ショーケース#26. 神谷絢栄 Ayae Kamiya《わたしの作り方》展示風景
ショーケース#26. 神谷絢栄 Ayae Kamiya《わたしの作り方》展示風景
実は神谷さんの表現には、アトラス展(秋の始まりに取手校地で開催される先端修士1年生の展示)の方で先に接していた。その時の作品は、性被害に対する自身の治癒ともいえるだろう気持ちの変化と、消えない記憶とを、母親や恋人といった近しい人との対話の形で記録したものだった。見る側はヘッドホンをつけて、書き起こされた応答を読み上げる形での本人と母親、本人と恋人、本人と友人との対話を聞く。彼女の作品を見た時、これをシェアする勇気に素直に感謝した。でもこの次に彼女に出会ったら、どう声をかけるといいんだろう、と思い悩んだ。そののちのショーケースの展示だった。
結論から言って、私は抱いた感想をうまく彼女に伝えることはできなかった。こうして作品という媒介で外界に投げ出せることが彼女自身の治癒なのかもしれないと思ったから、それにお礼を伝えるのもおこがましいと感じた。謝意を伝えて満足するのは私だけだということにも気づけた。
多様な異なる他者と居合わせるトレーニングの場をつくる、というのがアートプロジェクトの一つの役割だと思ってきた。このテキストで紹介した2作品のように、展示という形を取ることのできるアート作品が、展示物を媒介に見る人と社会との新たな関係を切り結ぶ役割を果たすのに対して、アートプロジェクトはそもそも形としてのモノがない。アートプロジェクトという仕組みをつくり、その中で、同じ場にいる人たちのリアルな衝突、面くらう体験を皮切りに、いままでにこの世界になかった、小さくて新しい関係性をつくるものだ。そのダイナミズムのなかにさまざまな違いがあればあるほど、生まれる関係は未知のものになって立ち上がる。そのときの土台になる仕組みは、乗り降り自由な舟のようでありたい、なんなら舟の上で新しい舟をつくることを考える人が出てきたらなお良いと。
しかしこうして書いていて、その舟に一緒に乗ったとき、自分の無意識の振る舞いが誰かを傷つけている可能性を思う。だからこそ、自分の言葉や態度が、意図せず他者への暴力をはらみかねないことに、怖くなるよと、不安だよ、と誰かに伝えて考えることをやめてはいけないんだろうと思う。うろたえるのを放棄しないことが、ただ一つ確かな道のように考えている。
そういう足場を、基礎を、確かめさせられるひと月の展示のことを、食堂の日々での定点観測として書き残します。
text: 羽原康恵(特定非営利活動法人 取手アートプロジェクトオフィス 事務局長)
banner: ちぇんしげ バナーについて
